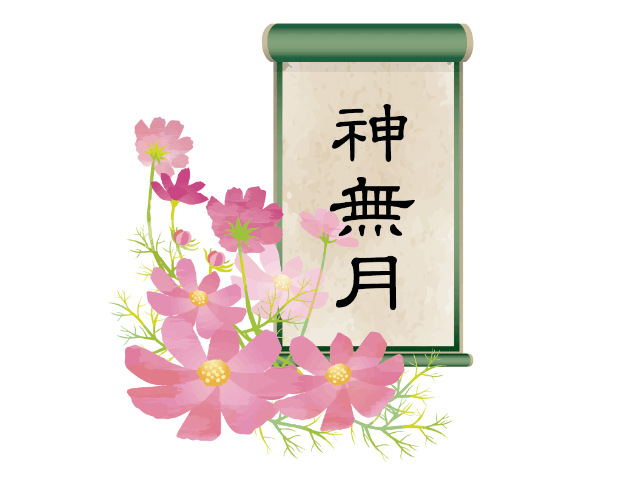
神無月(かんなづき)は和風月名の一つです。
神無月は何月?、その由来について6つの説を紹介します。
何月?

神無月は旧暦(太陰太陽暦)の10月のことを言います。
現在の新暦に置き換えると、10月下旬〜12月上旬ごろ。
旧暦と新暦では1ヶ月ほどのずれがありますが、現在では「10月の別名」としても使われています。
由来
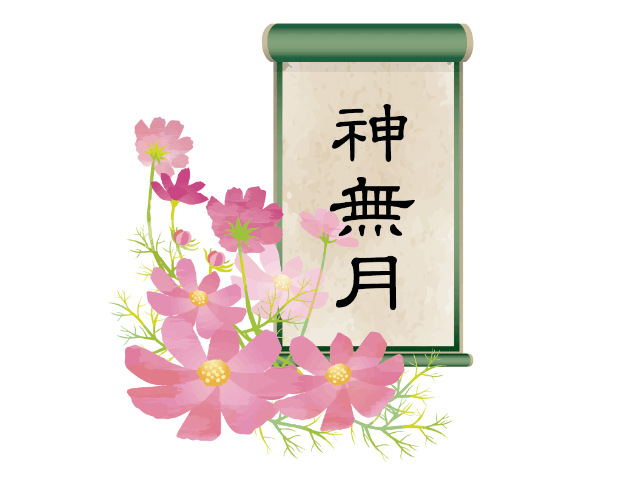
神無月の由来は諸説あります。
神様が不在の月

全国の神様が出雲大社に集まる月となっていることから「神無月(かんなづき)」となったという説があります。
逆に出雲地方では、たくさんの神様が集まることから「神在月(かみありづき)」と呼ばれ、神在祭、縁結大祭などがお祭りが行われます。
神無月と神在月について詳しくは下の記事にまとめています▼
神の月
神無月の「無」は「ない」ではなく、連体助詞の「な」という意味から来ています。
そのため、「神の月」という意味になるという説もあります。
これは6月の「水無月」と同じ使い方。
神嘗月(かんなめづき)
伊勢神宮では10月15日〜17日に「神嘗祭(かんなめさい)」が行われます。
これはお祭りの中で最も重要とされるお祭り。伊勢神宮のお正月とも呼ばれています。
その神嘗祭(かんなめさい)が行われる月であることから「神嘗月(かんなめづき)」と呼ばれ、それが転じて「神無月」となったという説もあります。
雷無月(かみなしづき)
旧暦の10月は、雷が鳴りにくい時期に入ります。
そこから「雷無月(かみなしづき)」と呼ばれるようになり、それが転じて「神無月」となったという説もあります。
醸成月(かもなしづき)
お酒を神様に捧げる時期であることから「醸成月(かもなしづき)」と呼ばれていました。
その「醸成月(かもなしづき)」が「神無月(かんなづき)」に転じたという説もあります。
お米を作り、刈り取り、お酒を作り、神様に捧げるというのが日本の文化としてあったのに由来しています。
上な月(かみなづき)
10月の神無月を「上な月(かみなづき)」と呼んでいました。
その「上な月(かみなづき)」が転じて「神無月(かんなづき)」となったという説もあります。
それに対し、11月は「下な月(しもなつき)」と呼ばれ、「下月(しもつき)」→「霜月」と転じた説もあります。
以上6つの説を紹介しました。神様と秋の収穫が大きく関係しているのがわかります。
この時期は十三夜、スポーツの日、紅葉狩り、ハロウィンなどの季節になります。
詳しくは「10月の年中行事」にまとめているので見て下さい。
