
師走(しわす)は和風月名の一つです。
師走は何月?、その由来について5つの説を紹介します。
何月?
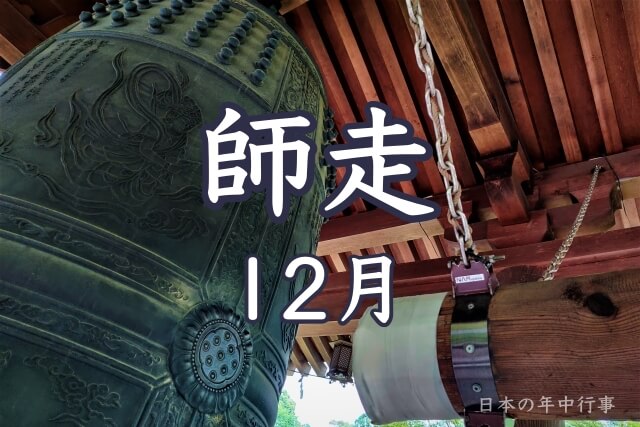
師走は旧暦(太陰太陽暦)の12月のことを言います。
現在の新暦に置き換えると、12月下旬〜2月上旬ごろ。
旧暦と新暦では1ヶ月ほどのずれがありますが、現在では「12月の別名」としても使われています。
由来

霜月の由来は諸説あります。
師馳す(しはす)
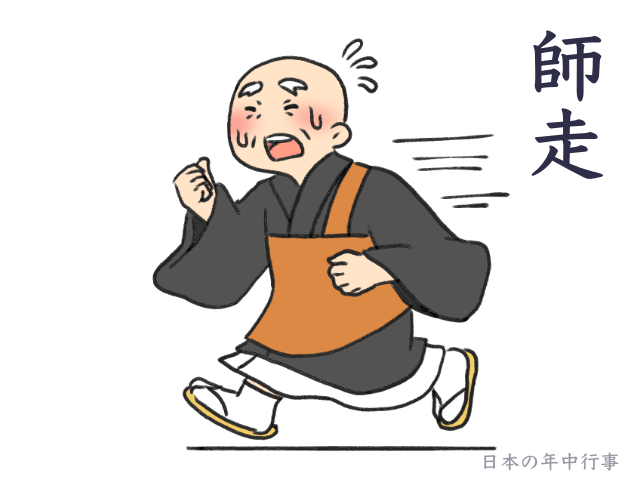
師匠の僧がお経をあげるのに忙しく、東西を馳せる月「師馳す(しはす)」が転じたという説があります。
平安時代末期の文献「色葉字類抄(いろはじるいしょう)」「奥義抄」「名語記」にも「しはす」の欄に注として説明されているから、最も有力となっています。
年果つ(としはつ)
年末であることから「年が果てる」という意味の「年果つ(としはつ)」が変化し、「師走(しわす)」となったという説もあります。
年が果てる(としはつる)月「年果月」と同じ意味で「歳極月」「歳終月」もあります。
四極(しはつ)
「四季が果てる月」を意味する「四極(しはつ)」が転じて、「師走(しわす)」となったという説もあります。
為果つ(しはつ)
「一年の最後になし終える」という意味の「為果つ(しはつ)」が転じて「師走(しわす)」となったという説もあります。
成終月(なしはつるつき)
江戸時代の文献「紫門和語類集」によると、1年を成し終える月「成終月(なしはつるつき)」が転じて「師走(しわす)」となったと書かれています。
以上5つの説を紹介しました。
最も古い文献に載っている「師馳す(しはす)」が最も有力。以降は色々な当て字を使って師走を言い換えています。
この時期は事納め、煤払い、年末年始、お正月の飾り付け、冬至、大晦日などの季節になります。
詳しくは「12月の年中行事」にまとめているので見て下さい。