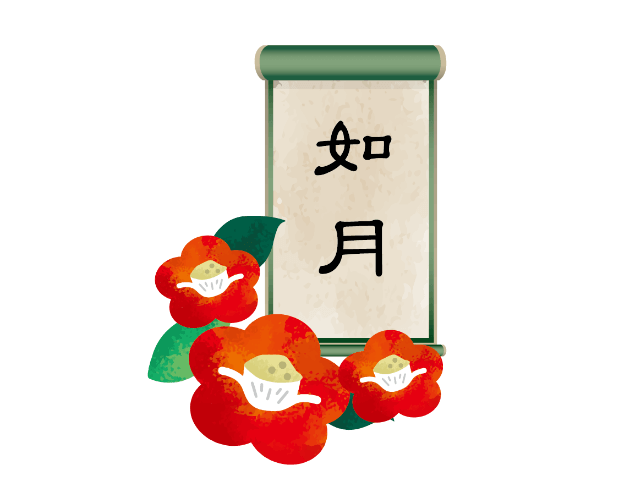
如月(きさらぎ)は和風月名の一つです。
如月は何月?、その由来について5つの説を紹介します。
何月?

如月は旧暦(太陰太陽暦)の2月のことを言います。
現在の新暦に置き換えると、2月下旬〜4月上旬ごろ。
旧暦と新暦では1ヶ月ほどのずれがありますが、現在では「2月の別名」としても使われています。
由来
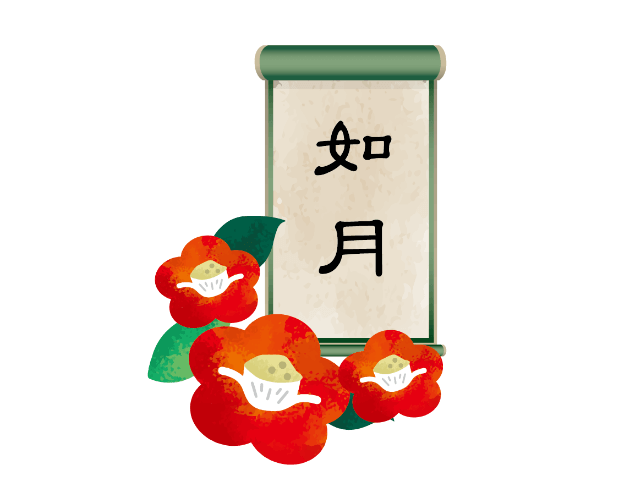
如月(きさらぎ)の由来は諸説あります。
衣更着(きぬさらぎ・きさらぎ)
暦上は春ですがまだ寒さが残るため、衣服を重ね着する「衣更着(きさらぎ)」が転じて、「如月(きさらぎ)」になったという説があります。
平安時代末期の歌人・藤原清輔(きよすけ)が「奥義抄」に『寒くて衣服を重ね着する月なので衣更着(きぬさらぎ)と言っていたものが、誤って「きさらぎ」と呼ばれるようになった』と記しています。
俳句季語辞典にも衣更着(きさらぎ)が載っています。
気更来(きさらぎ)
陽気が更に来るという意味の「気更来(きさらぎ)」が転じて、「如月(きさらぎ)」になったという説があります。
※陽気とは温かい気候のこと
生更木(きさらぎ)
春に向かって草木が更に生えるという意味の「生更木(きさらぎ)」が転じて、「如月(きさらぎ)」になったという説があります。
草木張月(くさきはりづき)

草木の芽が張り出す月という意味の「草木張月(くさきはりづき)」が転じて、「如月(きさらぎ)」になったという説があります。
二月を如となす
中国最古の辞典「爾雅(じが)」によると、「二月を如となす」という記述があります。
中国では2月のことを「如」と表していました。「如」とは「従う・赴く(おもむく)」という意味。
そこから「厳しい冬の季節が終わり、草木や動物など万物が動き出す季節」という意味で「如」があてられたとされています。
それが日本に伝わりました。「日本書紀」にも「きさらぎ」が出てきます。
以上5つの説を紹介しました。
この時期は節分、立春、初午、旧正月(春節)、バレンタインデーなどの季節になります。
詳しくは「2月の年中行事」にまとめているので見て下さい。